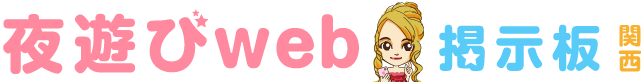-
夜遊び夜遊び
-
お水お水
-
ホストホスト
-
風俗風俗
-
ビューティビューティ
-
ファッションファッション
-
悩み相談悩み相談
-
モデルモデル
-
芸能芸能
-
雑談雑談
-
食べ物・グルメグルメ
-
生活生活
-
恋恋
-
インターネット・ゲームネット・ゲーム
-
ギャンブルギャンブル
-
過去ログ倉庫過去ログ倉庫
-
運営運営
『べらぼう』主人公「蔦屋重三郎」が、再起をかけてプロデュースした「浮世絵」とはどんなもの?浮世絵がカラーになったきっかけは、意外にも…(婦人公論.jp)

-
2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。横浜流星さん演じる主人公・蔦屋重三郎は、江戸の出版プロデューサー。敏腕編集者でもあった蔦重が見抜いて手掛けた、浮世絵、出版、芝居、グルメ、ファッションは次々と江戸の流行となりました。そんな「江戸のメディア王」が躍動した時代の本当の楽しみ方を、『蔦屋重三郎と江戸の風俗』より一部を抜粋して紹介します。
【書影】2025年NHK大河ドラマ『べらぼう』主人公の蔦屋重三郎が「江戸のメディア王」になった時代を、日本史深掘り講座が編集『蔦屋重三郎と江戸の風俗』
* * * * * * *
◆「浮世絵」をモノクロからカラーへ発展させたマニアたち
蔦屋重三郎は、「本」でも多数のヒット作を作りましたが、それらは約250年という歴史に埋もれて、今、読む人は少なく、一般にはほとんど知られていません。
一方、蔦重の手がけた「浮世絵」は、時代を超え、国境を超えて、今では世界的に知られています。
写楽の大首絵などは、ジャパンアートの代表格といえるでしょう。ここからは、蔦重の手がけた絵を中心に、浮世絵の歴史を振り返っていきます。
まず、「浮世絵」とは、「浮世」を描いた風俗画の総称です。江戸時代には「浮世絵」に限らず、「浮世草子」「浮世風呂」など、「浮世」のつく言葉がよく使われていました。
この「浮世」、戦国時代までは「憂世」と書かれ、「この世は憂うべき世」という意味で使われていました。
ところが、江戸時代、天下太平の時代を迎えると、「憂世」は「浮世」と表記されはじめます。
そこには、平和な世の中、楽しく浮かれて暮らそうではないか、そんな意味が込められていたようです。◆庶民の生活を描いた風俗画を「浮世絵」と呼ぶようになった
「浮世絵」の始祖は、江戸初期に活躍した菱川師宣(ひしかわもろのぶ)です。
肉筆画では、後述する『見返り美人図』などを描き、また「浮世絵版画」も手がけ、1670年代、「墨刷り絵」と呼ばれる白黒の版画をつくりました。当初の浮世絵は、カラフルなものではなく、墨1色刷りのモノクロ版画だったのです。
浮世絵の世界では、連作版画を「揃物(そろいもの)」と呼びますが、その出版スタイルを生み出したのも、彼でした。
師宣は、それまでは、本の一部(挿絵)でしかなかった版画を本から切り離し、独立のアートに変えたのです。「浮世絵の始祖」といってもいい存在でしょう。
ただ、そこから、私たちがよく知る多色摺り、フルカラーの浮世絵になって、人気を得るようになるまでは、約1世紀の時間を要しました。
そのきっかけは、浮世絵とは別のところにありました。明和年間(1764〜1722)、江戸の裕福な趣味人の間で「絵暦(えごよみ)」の交換会が流行したことが発端になったのです。
絵暦は、今でいえば、イラスト付きのカレンダーのようなもの。当時の暦(太陽太陰暦)では、毎年、何月が「大の月」で、何月が「小の月」なのか、一定していませんでした。
提供元:Yahooニュース